DTM中級者が覚えたい曲を良くするアレンジ駄目にするアレンジの違い
知らいないとヤバい!DTM編曲スキルが上がる3つのコツ
これらの記事はこちらにまとめました。
DTMで音楽を作っていると音がぐちゃぐちゃになって「よくわからない」状態になる人は多いです。しかしDTM初心者ではなぜごちゃごちゃになるのか?という理由がわかりません。
この記事ではDTM初心者であってもごちゃごちゃにならないためのミックスポイントをお伝えします。
たくさんの楽器を駆使して曲を作っても再生するもこもこで聞きづらく、迫力もないし、何よりもダサい!という経験は多くのDTMerが通る道なので心配いりません。適切な知識と技術を持てれば誰でもDTMでのミックスができるようになり、その結果エフェクトプラグイン等の選択も無駄がなくなります。
結論を先にいうと「ミックスとアレンジは同義語」です。よいミックスは良いアレンジで成り立ちます。悪いアレンジはどうやっても良いミックスになることはありません。
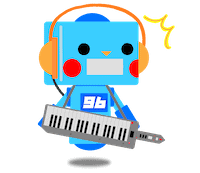
つまりミックス的な視点をもってアレンジするのがよいということ?

そのとおり!
ミックスとは
ミックス(ミキシング)とはドラムやギター、ボーカルにピアノ、様々な楽器のトラックをバランス良く聞けるようになる作業になります。
作業的には様々なエフェクトで精度の高いミックスにしていくイメージですが、大切なのはボリューム、パン、が基礎になり、イコライジングやコンプはより複雑なアプローチになります。
ミックスと同義になりつつあるのがマスタリングです。マスタリングはそれらを2mix(LとRにまとめられたもの)にしたものをよりよい音圧で聞けるようにするというのが最近の定義ですが、マスタリングはその後の再生フォーマットやアルバムなどの場合の音のつながり、音圧も含んだ作業になります。
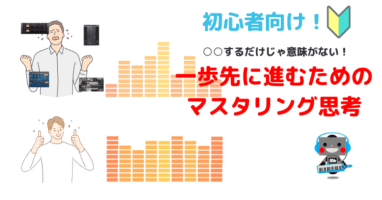
基礎①ミキサーの意味を正しく理解する
DAWによって表示方法は違いますがミキサー画面は次のような配置になっています。

このフェーダーStereo Out(ステレオアウト)に送る量になります。上記の画像ではKickだけを送っているので、フェーダーの位置及びメーターの位置も同じになります。(たまに0dBを超えてしまうこともありますが、おそらく0.1dB単位での超え方になります)
フェーダーを使って、ステレオアウトにどれくらいのバランスで送るのか?これがミキシングする上でもっとも基礎的な部分になります。
上記の画像ではキックだけしかステレオアウトに送っていないのでメーターの動きはステレオアウトとキックトラックの動きは同じになります。
基礎②ミックスはボリュームのみから始める
ミックス作業にはイコライザーやコンプ、マキシマイザーなどのプラグインを使って行うイメージがあるかもしれませんが、
最初からそれらのプラグインを駆使するのは得策ではありません。それらのプラグインはより良いバランスの上で成り立ってたものにフォーカスを当ててより見えやすくするものというイメージです。
最初から音源等にプラグインを挿したりマスターにマキシマイザーを挿したまま行う人もいますが、ミックスとは?と考えている人にはとにかく音量バランスです。音量バランスなくしてミックスは成り立たないという思ってちょうどよいでしょう。
しかし、そうは言っても音量の基本となる素材が決まらないと話にはなりません。私も含めて多くの場合、キックが音量のバランスの柱にしている人が多いです。
とくにダンスミュージックの場合、キックの音色一つですべて決まるというほどキックは重要です。キックの音色、音の消え際まで見えるためにはキックを音量バランスのスタート地点にするのが合理的です。
では音量はどれくらいが良いのか?ということになります。
これは音色によっても異なりますが、-10〜-8dBくらいにして他の楽器はキック以下にするとミックスが破綻するようなことはありません。
それぞれのトラックからまとまったステレオアウトのメーターは-6dB〜-3dBを空けるようにします。この空いた部分でマスタリングをプロセスを行います。

基礎③すべての音域を周波数で考える
すべての音程は周波数で表せます。それはドラムも変わりません。「イコライザーで何Hzを〇〇カット/ブーストしましょう」というのはすべてそのミックスに必要な音程を調整しているわけです。
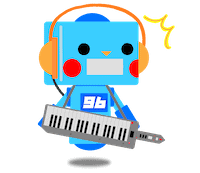
キックやスネアにシンバルも?

音はすべて周波数で表せられるよ
ノイズ成分が多いとそれだけ複雑な周波数が表示されますが、ボーカルや、ギター、ベース、ピアノ、シンセ、ストリングス。ドラム、などポップス等で使われる楽器の周波数はわりとわかりやすいです。
周波数はスペクトラム・アナライザーを使うと確認可能です。

音の倍音を知る



なんだかトゲトゲしたものがいっぱい

それらの一番左(低いところ)にあるものがここではC4の音だよ
スペクトラム・アナライザーで表示されたC4には多くのトゲトゲが見られます。一番左のものがC4の音になりますが、音には倍音と呼ばれる響きがあり、それが音色として重要な役目を果たします。
倍音についてはこちらの記事が参考になります。

イコライザーで音作りをするときにために「8kHzをブーストして」みたいな言葉を見かけるかもしれません。これは倍音を操作することで音のエアー感やきらびやかさなどを調整しているわけです。
ではなぜ、「8kHzがエアー感できらびやかさ」なのか?これこそが「音を周波数」で知るという部分に繋がります。
楽器の中で一番広い音域を持つ楽器はピアノであり音域は次のようになります。
| 一番低い音 | 一番高い音 |
| A0(周波数27.500Hz) | C8(4186.009Hz) |
すべての楽器はこの音域の中でのやり取りになります。
さて、ピアノの一番高い音であるC8の周波数は4186Hzです。先程のエアー感やきらびやかさである8kHzの半分が楽器の中で一番高い(実音)になるわけです。
この8kHz付近は音作りとしてとりあえず上げておこうみたいなイメージがありますが、他の楽器の倍音同士と干渉する場合は当然バランスを取る必要があります。

全部の楽器の倍音を上げるのではなく、聴かせたい楽器の倍音を調整し、それ以外はボリュームだけにすると、不必要なイコライジングを抑えられ耳にも優しく、なおかつ音の存在感をはっきり示せる音色になります。
基礎④必要なトラックだけを意識する
DTM中級者に限らず多くのDTMerがやってしまうのが音色詰め込み式のアレンジです。トラック数が多い方がいい!みたいなことを書籍で読んだりネットで情報集したりした結果だと思いますが、
トラックの多さは適材適所です。
無意味なトラック数は曲の良さを台無しにします。「自分は少しは音色をコントロールできるようなってきた」という思い込みがあるかもしれませなんが、まずは本当に必要なトラック数を意識するところから始めるのがオススメです。
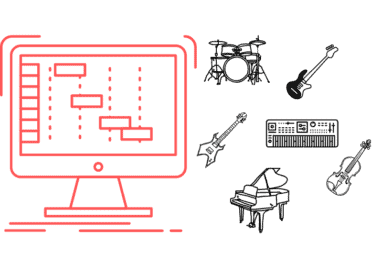
上記でも解説はしていますが、トラックの目安は16〜24です。このあたりのトラック数をしっかりとコントロールできるようになると無理のないミックスができるようになります。
基礎⑤中音域に音が集まらないようにする
よいミックスとは全体的にバランスの取れた音量調整になっていることと覚えるのは最初のステップです。
そして、その最初のステップで意識したいのが「特定の帯域に音が集まりすぎないようにする」ことです。
これは上記のトラック数とも関連しますが、トラック数が多いとどうしても同じ帯域に音が集まりがちになります。その帯域というのがミックスで最も難しいとされる「中音域」の処理です。
実は厳密な意味で何をもって「高域」「中域」「低域」と決まっているわけではありません。しかし大まかな目安として次のように捉えられていることが多いです。
- 高域は1kHz〜20kHz
- 中域は100Hz〜1kHz
- 低域は20Hz〜100Hz
そして最近は中低域、中高域というさらに細分化されています。グラフィックEQ(下記のような特定の周波数をピンポイントで上げ下げできるEQ)を扱う場合はかなり細かく周波数を扱える反面、慣れていない人には難しく見えることもあります。なのでそういう人はスペクトラム・アナライザー等を使って「中域」と思っている周波数「100hz〜1khz」の中で飛び出している部分を目で見ることをオススメします。

なぜ中域が団子状態になりやすいのか?
これは各楽器がどの音域なのかを考えるとわかりやすいです。
ギターの場合
- 1弦:330Hz (E4)
- 2弦:247Hz (B3)
- 3弦:196Hz (G3)
- 4弦:147Hz (D3)
- 5弦:110Hz (A3)
- 6弦: 82Hz (E2)
エレキベース(4弦)
- 1弦:98Hz (G2)
- 2弦:73Hz (D2)
- 3弦:55Hz (A1)
- 4弦:41Hz (E1)
6弦E2で刻むことで82hzの波形が出ます。倍音を持たないサイン波ではないので、E2を発音させれば第二倍音であるオクターブ上の164hzの倍音が発生します。ベースでE1の41hzも同じく第二倍音が出て82hzの音が出ます。そこにキックを鳴らした場合これまた60hz〜5khzくらいまでの音が発生しスネアであれば200hzにピークを持った音が出てきます。後はピアノやシンセにボーカルが増えつければどこが一番最初に音の渋滞を起こすかはわかると思います。
低域や中域は大型バスが通りまくっているそんなイメージでもいいかもしれませんね。エンジニアの渡辺紀明さんが周波数について触れています。「何を聞かせたいか」という意図がないままローカットを推奨するものではありません。そのことについて渡辺さんのツイートはわかりやすいと思います。
周波数帯域に音がかぶるのを防ぐ
音の団子状態を解消しようと思ったら「中音域」をいかにすっきりさせられるか?というのが答えになります。同じ音域に複数の楽器がいると楽器の輪郭が消えていきます。ベースとドラムがなったときにベースの輪郭が聞こえにくいがまさにそれです。
ギターやピアノで使われるコードの多くは中音域にあります。これを解消するためには
ギターでコード演奏をしている場合、ピアノをオクターブ上でコードを鳴らすか、ボイシングを変更して、できるだけ同じ構成音にしないことが重要です。
基本的にコード楽器は2つまで!これ以上すると音がこもって輪郭がはっきりしなくなるので注意が必要です。
基礎⑥パンニングによって左右に逃がす
ここまでボリュームのみと周波数だけの話をしてきたのには理由があります。ボリュームでしっかりとバランスが取れていればモノラルであっても聞けるミックスにはなります。つまりモノラルでバランスがしっかりと取れるのが理想ということになります。
ステレオにすることで今まで周波数同士でしか譲り合えなかった場所が「左右」に変わります。しかしステレオとは逃がす場でしょではなく、ステレオ抱けなければ行けない理由が必要になります。私はこれを「音場の演出」という考えたにしています。つまりミックスによる居場所を譲るのが目的ではなく、左右に広げることでどういう効果があるのか?という見方です。
一番わかり易いのは左右を確保することで「ワイド感」を演出できます。つまりより大きな絵をかけるようになった。という見方です。
モノラルとステレオでの楽器配置について
特殊な再生環境(モノラルでしか音が出せない)場合を覗いて音楽は基本ステレオで音楽を再生します。左右にあらゆる楽器を配置することで、音の場を見せてあげるわけです。こうすることで、一つ一つの楽器(音色)がよりわかりやすく伝わります。
歌ものの基準として中央に配置させる楽器は次の4つ
- キック
- スネア(ハイハット)
- ベース
- ボーカル
左右に広げる楽器はつぎの通り
- シンバル
- タム
- ギター
- ピアノ
- ストリングやブラス
- シンセ
これを基準に考えるだけでもすっきりとしたアレンジになります。
基礎⑥音の奥行き感をコントロールする。
楽器の配置を左右に配置するのがパンニングとするならば楽器の奥行き感をコントロールするのはイコライザーやコンプになります。
奥行きに関しては以下の記事で詳しく解説していますが、ここでは基本的に奥行きとはなにか?について説明します。
奥行きはアタックの距離によって決まると私が考えています。
「つまりアタックが強い音は近くに感じて、アタックが弱い音は遠くに聞こえる」この部分を意識するために例えばイコライザーでアタックが目立つ高域を少しカットするなどの方法を使うだけでも音の距離感は調整可能です。
ここで、コンプを多様しようものならばミックスの迷子に突入です。
アタック感である高域を少し下げるだけでも楽器の配置を少し下げることができます。

これを理解できると、コンプの使い方はより精度の高いものになります。またAUXなどを使ったリバーブによる音作りもよりイメージに近い音作りが可能になります


まとめ
とにかく不用意に音を重ねないことが大切です。スッキリとしたアレンジをできるようになればいくらでも音を重ねた編曲をしても音がこもるとういことはなくなります。
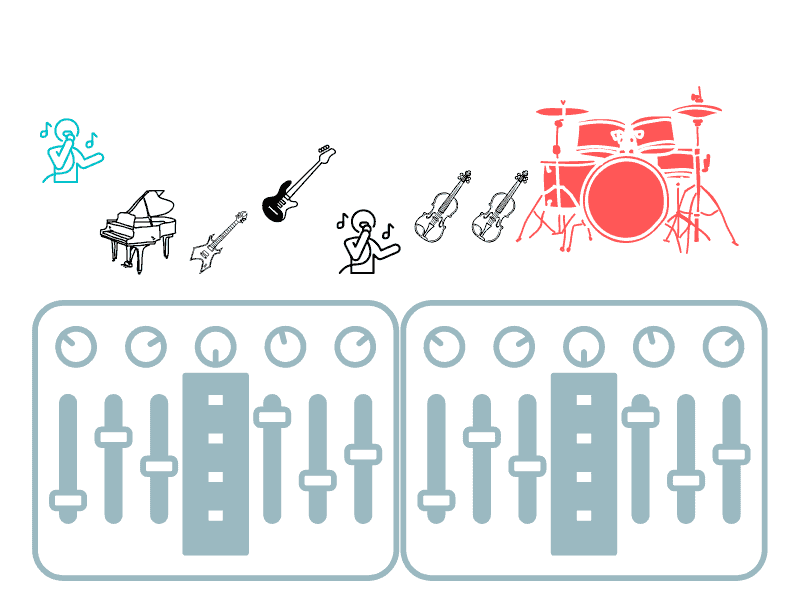



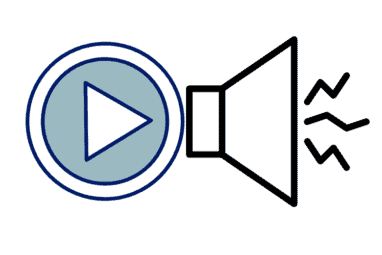



コメント