マスタリングのプロセスに挑戦しているけれど、理想のサウンドにならないと悩んでいませんか?
「マスタリング やり方」でお探しの方に、EQ調整からコンプレッション、必要なプラグインの選択まで、マスタリングを成功させるための具体的な手順とコツを紹介します。
この記事では、ミックスのバランスを整える方法、周波数帯域の適切な調整、そしてトラック全体の音量レベルを最適化する技術を解説。DAWを活用した効果的なマスタリングの進め方を学び、あなたの音楽制作を次のレベルへと引き上げましょう。
てっとり速くマスタリングで音圧をあげるやり方
もしつべこべいわずに「マスタリングで音圧をあげる方法を知りたい」という人は
DAW付属のマキシマイザーを2〜3段重ねて、それぞれのゲインリダクションが1.5dB程度、合計5〜6dB程度になるようにすれば音圧はわりと簡単にあげられます。
しかし、大切なのはミックスダウンで作った音量のバランスや空間的な演出をより微調整によりブラッシュアップすることです。
微調整とは具体的にどういうのものか? それは世界観のディテールを明確にする。2mixでまとまった音源の細部にフォーカスが当たるようにします。この作業が1.5dB〜2dBの範囲で行われる世界です。
このことから、マスタリング前にはこのマスタリング作業領域としてマスターアウトが最低でも3dB程度余白を残しておくことが大切になります。
リスナーが一回聞いたら「お腹いっぱいもういらない」数回聞けば「いや、マジ勘弁」という状態になるのは好ましい話ではありません何度も聞きたいと思わせることががマスタリングの成功です。
マスタリングの手順について
DTMでのマスタリングの手順多少エンジニアによって異なりますが、以下のような流れが一般的です。
- リファレンス曲の準備
- ミックスの最終確認
- マスタリング前に、ミックスのバランスを最終チェックします
- 必要に応じて微調整を行います
- イコライザー (EQ) の適用
- 全体的な音色バランスを整えます
- 不要な周波数をカットし、強調したい帯域をブーストします
- コンプレッションの適用
- 全体的なダイナミクスを調整します
- マルチバンドコンプレッサーを使用して、周波数帯域ごとに細かく調整します
- ステレオイメージの調整
- ステレオエンハンサーなどを使用し、音の広がりを調整します
- リミッターの適用
- A/Bテスト
- 異なる再生環境でのチェック
- ヘッドフォン、スピーカー、車内など、様々な環境で聴いてバランスを確認します
- 最終調整
- 書き出し
- 適切なフォーマット(WAV, FLAC等)で書き出します
マスタリングは繊細な作業なので、耳を休ませながら慎重に進めることが重要です。また、プラグインの使用順序や設定は曲によって異なるため、柔軟に対応することが大切です。経験を積むにつれて、自分なりのワークフローを確立していくことができるでしょう。
失敗するマスタリング見直しポイント
ここではマスタリングの失敗につながる手順について解説していきます。
①ミックスバランスを整えていない
結論から言うとマスタリングの失敗の8割はミックスのバランスです。さらに言うとミックスはアレンジによって決まります。まずは適切なバランスを心がけることが重要です。
ポイントは次の8つ
- キックのアタックがわかる
- ベースの音程とラインが見える
- スネアは大きすぎない(気持ち小さくてOK)
- ハイハットは少し耳をすますことでわかる大きさ
- シンバルはスネアより小さくするイメージ
- コード系の楽器はお互いを邪魔していない
- ボーカルは歌詞がすべてはっきり聞こえる
- コーラスはボーカルより一歩下がってしっかりとボーカルとのハーモニー感を作る
このミックスバランスを意識しながら、マスターフェーダーが-3dB付近になるようにすればバランスが整います。
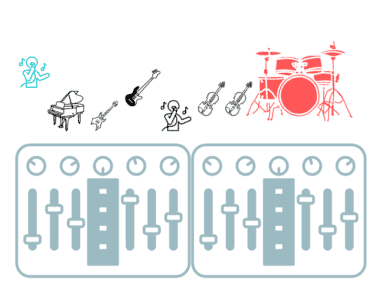
②トラックに不必要なエフェクトプラグインの使いすぎ
キックでありがちなのが50Hzをイコライザーでブーストするというパターンですが、これほんとうにブーストする必要があるのか?という話でもあります。
例えば、EDM系のエレクトリックなキックの多くは最初から50Hz帯域が多く含まれているものがあります。このようなキックにイコライザーで50Hzをブーストすると
低域がモヤモヤするだけの音になる可能性が大きいです。
また、キックが16分音符であるハードロックの場合必要以上の低域はスピードが失われます。このように「キックだから低音をブースト」するという考え方から「この音色にはそれが必要なのかな?」という意識をもつことの方がプラグインを使うより遥かに重要です。
③バス・トラックを使っていない
ミックス時にバストラックを使わないとすべてのアウトがマスターに集中してしまいます。これではすぐにマスタートラックはレベルがオーバーしてしまいます。
ドラム、ボーカル、ギター、シンセ、などをまとめたバス・トラックを使うことでマスタートラックに余裕をもたせることができます。
参考記事
DTM初心者が悩むBUSとAUXの違いと効果的な使い方について
④マスタートラックでエフェクトの使いすぎ
マキシマイザーやイコライザーに加え、エキサイターや更にコンプを使う必要はありません。
基本、イコライザーとコンプ(マキシマイザー)で十分に目指す音圧を稼げます。
マスタリングが上手く行かない人の多くは参考サイトや教則本を見て「プラグインを5つ使っているから」という理由で使うことが多いですが、まずはイコライザーとコンプでマスタートラックをまとめられるようにするのが先決です。
それでも複数使う場合もあります。例えばコンプの二段かげが良い例ですこの場合、ゲインリダクションが2つ合わせて3dBにするこのような使い方をします。
⑤プリセットを無意味に使ってしまう
マスタリング用のプリセットは便利ですが、あくまで参考程度に使うべきです。プリセットは汎用的な設定であり、あなたの曲に最適化されているわけではありません。プリセットを使う際の重要なポイント:
- 近似値として捉える: プリセットが音源に効果的かどうかを判断する目安にします。
- 鵜呑みにしない: 単にジャンルに合わせてプリセットを選ぶのではなく、音への効果を意識します。
- 適度な調整: 例えばコンプレッサーの場合、ゲインリダクションが3dB以上にならないよう注意します。
- 世界観の意識: 曲の世界観をイメージしながら、プリセットを自分の音を探すための道標として活用します。
プリセットは便利なツールですが、最終的には自分の耳と判断で調整することが大切です。
⑥プラグインの接続方法が適当になっている
マスタリングにおいて「どんなプラグインを指すのか」も重要ですが、どの順番でプラグインを指していけばどういう効果があるのか?ということを知っておくことです。

この画像が意味しているのはコンプのかかりをより効果的にするためにEQを指しているということになります。
つまり下段にあるプラグインの効果を上段のプラグインが補うと思ってください。

プロのエンジニアがエフェクトを使う際の重要なポイントは、各エフェクトの役割を明確にすることです。代表的な組み合わせ方には以下があります:1. コンプ → EQ の場合
- コンプで音の粒を揃え、EQの効きを良くします
- コンプ設定: スレッショルドを低めに、レシオは1:4程度
- EQは曲の特性に合わせて選択
2. EQ → コンプ の場合
- 低音が強い音源で使用
- EQでローカットし、コンプの効きを改善
重要なのは、エフェクトを使う目的を明確にすることです。単に「コンプとEQをかける」だけでは効果がありません。音源の特性や目指す音を考慮し、適切なエフェクト処理を選択することが大切です
⑦アレンジが整っていない
意外に思う人が多いのですが、これが一番重要です。音圧を上げることを目的とするのではなくすべての楽器がバランスよく聞こえることができる。
これが良い曲の良いミックスの定義でありそれをよりよく整えるのがマスタリングの仕事になります。
よく勘違いしている人が多いのは「音がこもってしまってもマスタリングでなんとかなると思っている」人が多いですが、マスタリングは「微調整」の世界です。こもった状態のミックスからクリアなサウンドはマスタリングで解決はできません。
その場合はアレンジレベルやミックスまで戻ってこもっている原因を突き止めなければいけません。
今はプラグインでどんなアレンジであっても無理やり音圧を上げてしまえますが、マスタリング工程で「何か違う」と感じたらすぐに全体のバランスがきれいに聞こえるアレンジが出来ているかを確認する必要があります
マスタリングとは?
DTM(デスクトップミュージック)におけるマスタリングは、音楽制作の最終段階で行われる重要な工程です。
このプロセスでは、ミックスダウンされたトラック全体のサウンドを調整し、音楽の品質を最終的に磨き上げます。マスタリングには、EQ(イコライザー)による周波数のバランス調整、コンプレッサーを使ったダイナミクスの管理、必要に応じて特定の帯域のブーストやカット、そして全体の音量レベルを適切なdBに調整する作業が含まれます。
DAW(デジタルオーディオワークステーション)上で行われるこのプロセスには、様々なプラグインが使用されます。
これらのプラグインには、マキシマイザー、EQ、コンプレッサーなどがあり、楽曲の音質を向上させるために必要な調整を行います。また、ボーカル、キック、ベースなどの主要な音源に対して、MS(ミッドサイド)処理やステレオイメージの調整など、さらに細かなエフェクトを加えることもあります。
マスタリングの目的
マスタリングの目的は、楽曲をあらゆる再生環境やメディアで一貫した音質で聴けるようにすることです。
そのためには、録音からミックス、そしてマスタリングに至るまでの各段階で、音楽制作における基本的な手順とプロのエンジニアによる緻密な作業が必要とされます。プリセットを活用しつつも、楽曲のイメージやアーティストの意図に合わせた適切な方法で調整を行うことが、成功したマスタリングの鍵となります。
DTMでは主に音圧処理的なイメージが強いですが、(CD、DVD、Blu-ray Disc、LPレコード、ビデオテープなど)に収録し、量産用プレスをする際のマスター(原盤)を作成する作業というのが本来のマスタリング処理となります。
本来は複数の曲のバランスをとることが主な目的ですが、最近は一曲の音圧を限界まで上げることがマスタリングの目的と理解されている傾向にあります。
一曲の音圧を限界まで上げる事自体を悪いとは言いませんが、過度に音圧が高くなった音楽=最良のマスタリングと考えるとマスタリングはうまくいきません。
例え個人で楽しむものであっても「誰が聴いてもバランスが取れていて心地よい音楽にする」ということをマスタリングと考えていくのが失敗しないマスタリング方法の基本的な考え方です。
失敗しているマスタリング方法とは?
音が飽和している
音圧を重視しすぎた結果ダイナミクス系のプラグインを使いすぎて音が飽和(潰れ過ぎている)している状態はマスタリングは失敗です。
そのような音楽は「息苦しい」「音が窮屈」「奥行きがない」このように形容されます。
本来マキシマイザーでは音は割れないように設計されていますが、それが割れているということは明らかに使い方が失敗しているということになります。
音圧の目安は
音圧が高い!と言われても具体的にどれくらいの音圧が正しいのかわからないと思いますし、ジャンルによっても音圧は違います。音圧はLUFSという値を参考にします。多くのDAWにはレベルメーター的なプラグインがあるのでそれでこのLUFSを計測します。
多くのストリーミングサイトが-14LUFSになっているのを参考にしながら、今作っているジャンルのリファレンス曲のLUFSを参考にすると良いでしょう、
DAWによってマスタリングは異なるの?
「CUBASEマスタリング」「LOGICマスタリング」そのほか、StudioOne、Protools、などDAWの数があればマスタリングのやり方は違うと思ってしまう人もおおいでしょう。
しかし、基本的にはマスタリングの方法論はどのDAWを使っても同じです。
DAW付属のマスタリングプラグイン(主にマキシマイザー系をさす言い方)のクオリティにはそれぞれの個性がありますが、それ以外で何かが変わるということはありません。
なので、マスタリングだから「Protoolsが必要」ということはまったくありません。手持ちのDAWでやりたいことをしっかり意識できれば問題はありません。
LogicProXでの具体的なマスタリング方法について知りたい人はこちらの記事を参考にしてください。
純正のプラグインだけを使ったマスタリング方法です。

まとめ
マスタリングはマキシマイザーを使って音圧を上げて終わり!ではありません。
大切なのは曲の細かい意図をユーザーに届けるための微調整です。
フェーダーバランス等が整った上で
- 2mixの余計な帯域を削るEQ処理、
- より聞こえやすくするためのコンプ処理、
- アナログによる味付け、空間処理(ステレオ処理)
大胆な音の処理は2mixになる前にやっておくべきで、2mix後は微調整する
このように考えればマスタリングのやり方が大きく間違うことはありません。
